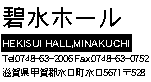ドイツ1919〜1931映画回顧展(1995年11月)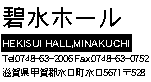
■ M ■■■■■■■■■■■
M−Eine Stadt sucht den M
1931年/白黒トーキー/100分
日本語字幕付
脚本:フリッツ・ラング、テア・フォン・ハルボウ(エゴン・ヤーコプゾンの記事による)
撮影:フリッツ・アルノー・ヴァーグナー
美術:エーミール・ハスラー、カール・フォルブレヒト
音楽:エドヴァルド・グリーグの「ペール・ギュント」のモチーフ
製作:メロ映画
出演:ペーター・ローレ(人殺し)、オットー・ヴェルニッケ(ローマン警部)、グスタフ・グリュントゲンス(シュレンカー)、エレン・ヴィートマン(ベックマン夫人)、インゲ・ラントグート(エルジー・ベックマン)、エルンスト・シュタール=ナーハバウアー(警察署長)、フランツ・シュタイン(大臣)、テーオドール・ロース(グレーバー警部)、フリードリヒ・グナス(押し込み強盗)、フリッツ・オーデルマル(いかさまとばく師)、パウル・ケンプ(すり)、テオ・リンゲン(ポン引き)、ゲオルク・ヨーン(盲目の風船売り)、カール・プラーテン(警備員)、ゲルハルト・ビーネルト(私服刑事)、ローザ・ヴァレッティ(場末の酒場の女将)、ヘルタ・フォン・ヴァルター(売春婦)、ルードルフ・ブリュームナー(弁護士)、ヨーゼフ・ダーメン、エルゼ・エーザー、イルゼ・フュルステンベルグ、ハインリヒ・グレートラー、アルベルト・ヘルマン
【解説】
この作品は、ウーファと手を切ったフリッツ・ラングが、ネーヴェンツァールの「ネロ映画」社で作った最初のトーキー映画であり、全ドイツ映画の中でベストの作品と評価されている映画である。素材は警察記録からとられた。特に、当時のドイツを騒がしていた二つの大量殺人犯人に対する裁判が、ラングの興味をそそった。一つは肉屋のハールマンの事件であり、もう一つは「デュッセルドルフの妖怪」キュルテンの事件だった。ラングは言う。「彼らのどちらも子供殺しではなかった。当時ブレスラウで子供に対する恐ろしい犯罪が起きていた。映画の主題は殺人犯の断罪ではなくて、母親に対する警告だった」。つまりラングは決まりきった探偵物の型を破ろうとしたのである。それは犯人を追い詰めるのが犯罪組織の一団であることによって、更に強められた。それはまさに1931年という危機の時代をもっともよく具現していた。その点をこの映画の核心として評価するならば、この映画はあらゆる点で抜群の出来映えであり、傑作としての条件を具えている。
トーキー初期の映画であることを考えると、音の効果的な使用法は驚嘆にあたいする。さらにダイアローグも犯罪組織との場面と警察の場面が見事に統合され、一つの全体を構成している。さらにベルリンの町のトーンが誇張もされず、美化もされず、これほど見事に構成された例も多くはない。そしてひ弱さと残忍さを兼ね備え、その大きなおびえたような眼で、「危機の時代」の人物そのものを表現した主役のペータ・ローレと、犯罪組織のボスを見事に演じたグスタフ・グリュントゲンスは、同時に「次の時代」を予感させる新しい演技人の出現を示していた。その意味ではこの映画は、1930年代の「人間喜劇」だった。逆行していく社会が生み出した「退歩する反逆者」の、もっとも適格な映像化…そこにこの映画の、今日までの持続する価値がある。
ドイツ1919〜1931映画回顧展(1995年11月)