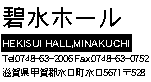ドイツ1919〜1931映画回顧展(1995年11月)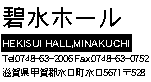
■死滅の谷■■■■■■■■■
Der m歸e Tod
1921年/白黒サイレント/85分
スライド日本語字幕付/音楽付
脚本:フリッツ・ラング、テア・フォン・ハルボウ
撮影:フリッツ・アルノー・ヴァーグナー(ベニス、オリエント、中国の部)、エーリヒ・ニッチュマン、ヘルマン・ザールフランク(古いドイツの部)
装置:ローベルト・ヘールト、ヴァルター・レーリヒ、ヘルマン・ヴァルム
製作:デークラ・ビオスコープ社
監督:フリッツ・ラング
出演:ベルンハルト・ゲツケ(死神)、リル・ダーゴヴァー、ヴァルター・ヤンセン(恋人同士)、ハンス・シュテルンベルグ(市長)、エルンスト・リュッケルト(牧師)、マックス・アーダルベルト(公証人)、エーリヒ・パプスト(教師)、パウル・レーコップフ(寺男)、エドガー・クリッチュ(医師)、ヘルマン・ピヒャ(洋服屋)、ゲオルク・ヨーン(乞食)、マリア・ヴィスマール(老婆)、アロイジア・レーネルト(母)
オリエント物語:リル・ダーゴヴァー(ゾベイデ)、ヴァルター・ヤンセン(フランク人)、ベルンハルト・ゲツケ(エル・モト)、ルードルフ・クライン=ロッゲ(イスラム教の托鉢僧)、エードウァルト・フォン・ヴィンターシュタイン(カリフ)、エーリカ・ウンルー(アイシャ)
ベニスの物語:リル・ダーゴヴァー(フィアメッタ)、ルードルフ・クライン=ロッゲ(ジロラーモ)、ルイス・ブロディ(ムーア人)リーナ・パウルゼン(乳母)、ヴァルター・ヤンセン(フランチェスコ)
中国の物語:リル・ダーゴヴァー(ティアオチェン)、ヴァルター・ヤンセン(リャン)、ベルンハルト・ゲツケ(弓術家)、パウル・ビーンスフェルト(アヒ、魔術師)、カール・フスツァール(皇帝)、マックス・アーダルベルト(大蔵大臣)、ノイマン−シューラー(刑史)
【あらすじ】
18世紀はじめ、ある古いドイツの小さな町へ、愛し合っている若い男女がやってくる。途中で一人の見知らぬ男が馬車に乗り込んできて、2人をじろじろ眺める。のちに2人は目的地の旅館で、再びこの男に出会う。彼は町の有力者たちにとっても、不気味な人物である。しばらく前に彼は町に現われ、墓地の近くの土地を買い入れ、その土地の周りにドアも窓もない高い壁を巡らしたのである。
さて旅館に泊った娘が子供たちと遊んで目をそらしている間に、恋人の若者はあの男に連れ去られてしまう。絶望した彼女は恋人を探して壁のところへ来て、気を失う。ある薬剤師が彼女を見つけて、家へ連れて帰る。そこで彼女はある本の中に「愛は死よりも強し」という文章を読む。そして毒杯を飲もうとする。
だが唇をコップに触れようとした瞬間、彼女は突然あの巨大な壁の前にいる。そこには入口が一つある。彼女はそこをとおり、長い階段を上がって行くと、一番上にあの見知らぬ男が待っている。それは死神だった。彼女は彼に自分の恋人を返してくれと頼むと、死神は彼女を大きなろうそくで一杯の巨大な会堂に連れていく。ろうそくはいずれも一人の人間の生命の代わりだった。死神は「私は人間の苦しみを一緒に見ることに疲れた。私は私の職業を憎んでいる」と言い、彼女にチラチラ揺らいでいる3本のろうそくを示す。それは死期の迫っている3人の若者の生命のろうそくだった。彼らも彼女の恋人と同様若い娘に愛されていた。死神は彼女に、この3本の中の1本を燃え尽きないよう守ることができたら、彼女の恋人の生命は助かるだろうと言う。こうして3つの物語が始まる。
第1のろうそくの物語では、彼女は9世紀のバグダットの町のカリフの娘ゾベイデとなり、若いフランク人を愛している。彼女が異教徒と関係していることが露顕すると、そのフランク人は逮捕される。絶望的にゾベイデは彼の生命を救おうと試みる。カリフは庭師のエル・モトに命じて、彼を生き埋めにさせる。ゾベイデがやってきた時は、すでに、遅すぎた。彼女はエル・モトの顔を知っていた。それは死神だった。
第2のろうそくの物語では、彼女は14世紀のベネチアの娘フィアメッタである。彼女は若いフランチェスコを愛しているが、しかし意地の悪い老ジロラーモと婚約している。ジロラーモは彼女に、「私は、彼女が私を憎んでいることを知っている。しかし結婚すればあなたは私を愛することを学ぶだろう」と言う。そしてジロラーモがフランチェスコの命を狙っていることがわかったので、フィアメッタは忠実なムーア人をそそのかして、彼女と一緒にジロラーモを罠にかけ、彼を毒を塗った剣で殺そうと企てる。だがジロラーモはその陰謀を見破り、フランチェスコが毒を塗った剣の犠牲になるように、ことを運ぶ。
古代中国で演じられる第3のろうそくの物語では、彼女は魔術師アヒの娘ティアオチェンである。そして助手のリャンに恋している。魔術師が宮廷でその術を演じた時、皇帝はティアオチェンに興味を示す。しかし優しくしても、力づくでも、彼女は応じない。皇帝を怒らせたティアオチェンは、とうとうリャンと共に象に乗って逃げ出す。皇帝の派遣した軍隊はしかし追いつかない。そこで皇帝は、アヒが贈った魔法の馬を弓術家に与え、生死にかかわらず彼女を連れ帰るようにと命ずる。死神の顔をした弓術家は天空をかけ、一瞬にして2人に追いつく。そこでティアオチェンは父から習った魔術を使って彫刻に変身し、リャンを虎に変える。弓術家は虎をたおす。彫象の頬から血の涙が流れる。こうして3本のろうそくの火は消えてしまう。
しかしどうしても恋人を取り返したい彼女は、もう一度死神の慈悲を懇願する。そこで死神は彼女に最後の機会を与える。もし彼女が他の人間の生命を持って来たら、喜んで彼女の恋人の生命を返してやろうというのである。ここで束の間の夢が終わる。老薬剤師は彼女の口から毒杯をさっと奪い去ってしまう。そして彼は自分はもう人生に飽き果てていると口をすべらす。そこで喜んで彼女があなたの生命を自分の恋人のために犠牲にしてくれないかと頼むと、彼は怒って彼女を叩き出してしまう。疲れ果てた乞食も、病院にいるよぼよぼの老婆たちも、犠牲になってくれないかと尋ねると、真っ平だと断わる。
その時病院に火事が起こる。入院患者が逃げてしまってから、赤ん坊が一人残されていることがわかる。母親の悲しみに打たれた彼女は、炎の中へ飛び込んで行く。彼女が赤ん坊を抱き上げた瞬間、死神が約束通り手を延ばして、この生命を取ろうとする。しかし彼女は約束をやぶる。自分の恋人の命をあがなうのを止めて、赤ん坊を窓の外に差し出し、母親に手渡してやる。焼け落ちる建物の燃え上がる火の真ん中で、死神は彼女を死んだ恋人のところへ導いていく。そして2人を生の緑の丘の上へ解放する。
【解説】
この映画はサイレント時代のドイツ映画を代表する監督の一人、フリッツ・ラングの名声を確立するのに決定的な意味を持った、最初の作品である。そこにはロマンティックな気分と、同時に宿命感が支配している。その両義性のために、一般にはこの映画の結末は、S・クラカウアーをはじめ多くの人々によって、「永遠に一つとなった2人の魂は、花咲く丘を超えて昇天して行く」と解釈されている。フリッツ・ラングの映像の力は、まさにそうした両義的解釈を許すアンビバレンスの中にある。すでに「疲れた死神」と言う原題名がアイロニカルである。人間の運命を死によって中断するという役目に「疲れた」死神は、2人の恋人を天国で結ぶことにしたのか、それともそうした役目を放棄して、緑なす生の野に解放したのか?
ラングは第1次大戦に将校として出征し、負傷して野戦病院で、もっぱら死を扱ったシナリオを書き始めた。こうした体験をした同世代の著作家の多くが書いたのは、平和主義的、表現主義的な絶叫だった。しかしラングは最初からラングだった。彼は映画を作るとは、一つの神話を作ることだということを知っていた。新しい諸体験は彼の場合、古い神話学の中に入り込み、それを革新する力を与えた。
彼はずっと死と少女の問題を扱っていた。つまり『死滅の谷』は、何も第1次大戦の前線経験によって、突如として出来上がった作品ではない。ラファエロが自分のマドンナ像を模索してさまざまな画像を残したように、ラングも自分のテーマをさまざまに展開するプロセスを辿っていたのである。第1次大戦の経験は、きわめて単純だったテーマの処理の仕方を、遥かに豊かにするのに役立った。それゆえこの映画を価値あるものにしているのは、基本的には同じ「死と乙女」のテーマではなくて、詩的な映像によって喚起される気分の多様な色調である。ルイス・ブニュエルは後に、ラングの『死滅の谷』は映画の詩的表現力に対する目を開いてくれた、と述べている。ヘルベイト・イェーリングは、ラングはこの映画によって、映画のために叙情的バラードというジャンルを発見したと述べた。この映画の宿命論を政治的無関心に通ずるものとしたクラカウアーでさえ、「『死滅の谷』の比喩的表現が保った長い生命力は、すべてが移動できない手回しのカメラで処理せねばならず、さらに夜間撮影はまだ不可能であったことを考えると、それだけ一層驚嘆に値する。これらの映像のヴィジョンは、きわめて正確なので、時として実在のものではないかという錯覚を起こさせるほどである。<蘇生させられたスケッチ>ともいうべきベニスのエピソードは、純粋なルネサンス精神をよみがえらせ、たとえば、カーニバルの行列やスタンダールやニーチェ流の、輝かしく残忍な南国の情熱を発散する、はなやかな闘鶏の場面を通じてそれを見せてくれる。中国のエピソードには、摩訶不思議な離れ業があふれている。ダグラス・フェアバンクスが、この場面の魔法の馬や、リリパットの軍隊や飛ぶじゅうたんに刺激されて、同じような魔法のトリックをつかったスペクタクル・レビュー『バグダットの盗賊』を作ったことは、よく知られている」と賞賛している。エピソードだけでなく、本筋のハンドルンクも、きわめて印象的である。ドイツの小さな町の古風なたたずまいと死神の館の重々しい雰囲気、そして何よりもあの巨大な壁の圧倒的な迫力。その点では『カリガリ』のセットを作ったヴァルター・レーリヒ、ノヘルマン、ヴァルム、ローベルト・ヘールトのトリオの手に成るセットの絶妙な光の効果が、大いに威力を発揮している。彼らはここでも『カリガリ』の場合と同様に、すぐれた仕事をしたと言える。
映像の印象深さに比べて、映画が示唆している神話学の方は、甚だ曖昧である。ドイツ的な宿命論と漠然としたカトリック的神秘主義の混合は、形而上学としては通俗的である。しかしフリッツ・ラングとテア・フォン・ハルボウ夫妻の個人的性癖とも言うべき、こうした通俗的神話学は、甚だ怪しげなものであるにもかかわらず、映像言語としてはかえって効果的だった。映像表現は叙事詩や楽劇とは違った神話を展開することはできなかった。その変わり神話を幻想的な美しいヴィジョンに変容することに成功した。
【エピソード】
フリッツ・ラングの特色。彼は映画を監督するのではない。彼は新しい世界を創造するのである。それにはお金がかかる。そのお金を食うのは大セットではなく、果てしなくゆっくりと、果てしなく念入りに仕事をするフリッツ・ラングである。彼は一つのシーンを、10回、あるいは20回撮影する。何もかも彼の気に入らない。すべては、もっと良く、もっと完全にできるはずだ。彼の協力者たちは、じきに挫折しそうになる。しかし彼らは、陰で悪口を言っても、やはりフリッツ・ラングに驚嘆しているのだ。彼は独特の人間である。彼は他の監督たちとはまったく違っている。彼は、エルンスト・ルビッチのように商売に興味はない。彼は自分の幻想に生命を吹き込もうとする。なにものも彼が想像しているものと違ってはならない。
彼は憑かれている。彼は妥協しない。驚くべきことは、彼が光の取り扱いを心得ていることである。人間が突然立ち現われたり、あかりが、いわば無から取り出されたりする様子…小さな路地、あるいは運河の雑踏を写し出すことによってではない。ルビッチであればそうしたかもしれない。さりとてサン・マルコ広場をそっくり作ることによってではない。ヨーエ・マイだったらそうしたかもしれない?そうではなく、水に沈む数段の石段によってである。1本のせまい運河の中に消えていくゴンドラによってである。
フリッツ・ラングは夜も寝ずに考えたトリックを使うが、それは後に常識になる。たとえば、中国でのエピソードの中に恋人たちの逃走の場面がある。恋人たちは、象に乗って皇帝から逃げようとする。皇帝は射手に、彼らに追いつけと命令する。射手は黒馬に乗り、雲を突き抜けて走る。そして死の矢が男を刺し貫く……。すべてこうしたことは、当時は新しく、センセーショナルである。しかしラングにとって、センセーショナルな効果をあげることは、まったく問題ではない。彼は何を望んでいるのか?彼は、最大にして最高の緊張度のあるストーリーを語りたいのである。彼は、自分の登場人物たちが、スクリーンを超えて観客の中へ入って行くのを望んでいる。彼は、彼らが観客の心を、息つくこともできなくなるほどとらえてしまうことを望んでいる。『カリガリ博士』と同様、主演女優は再び美しいリル・ダーゴヴァーである。死神を演じるのは、俳優ベルンハルト・ゲツケである。彼はこれ以後、ラング映画には必ず出演するようになる。
この映画はベルリンで封切られた時には、それど成功はしない。あるベルリンの新聞の批評の見出しにいわく、「退屈な死神!」。パリではもちろんこの映画はセンセーションになる。「真にドイツ的」と、パリの批評家たちは評する…つまり、「深遠」で「芸術的」だというのだ。そうするとドイツでも成功になる。この成功は何年もの間続く。33年後、1954年に、この映画はベルリン・デルフィ・パラストでもう一度上映される。テア・フォン・ハルボウが前置きを話す。映画館を去る時、彼女は足を滑らせる。ほんの数日後、彼女はこの転倒が原因で死ぬ。これが、「疲れた死神」を扱った、大いに論議を呼んだ映画の、本当の終りである。
ドイツ1919〜1931映画回顧展(1995年11月)