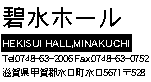ドイツ1919〜1931映画回顧展(1995年11月)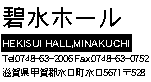
■嘆きの天使■■■■■■■■
Der blaue Engel
1930年/白黒トーキー/108分
日本語字幕付
脚本:ローベルト・リープマン、カール・ツックマイヤー、カール・フォルメラー(ハインリヒ・マンの小説「ウンラート教授」による
撮影:ギュンター・リッタウ、ハンス・シュネーベルガー
美術:オットー・フンテ、エーミール・ハスラー
音楽:ヒリードリヒ・ホレンダー
製作:ウーファ映画
出演:エーミール・ヤニングス(イマヌエル・ラート教授)、マレーネ・ディートリヒ(ローラ・ローラ)、クルト・ゲロン(奇術師キーペルト)、ローザ・ヴァレッティ(グステ)、ハンス・アルバース(マゼッパ)、ラインホルト・ベルント(道化役)、エードウアルト・フォン・ヴィンシュターシュタイン(学校長)、ハンス・ロート(小使い)、ロルフ・ミュラー(アングスト)、ローラント・ヴェルノ(ローマン)、カール・バルハウス(エルツム)、ローベエルト・クライン=レルク(ゴルトシュタウプ)、カール・フサール=プフィ(亭主)、ヴィルヘルム・ディーゲルマン(キャプテン)、ゲルハルト・ビーネルト(警官)
【解説】
今日すっかり神話となってしまったマレーネ・ディートリヒの伝説的な形姿を初めてスクリーン上に登場させたこの映画は、考えて見ればまことに奇妙な映画である。映画がトーキーになったことで存亡の危機に立たされたウーファが、アメリカから監督のジョセフ・フォン・スタンバーグと俳優のエミール・ヤニングスを呼び戻し、起死回生をねらって作った、事実上のドイツ・トーキー映画第一作。英語に比べて不利なドイツ語というハンディを克服するための手段としての、主題歌戦略…そのために起用されたのがカバレット・シャンソンの第一人者フリードリヒ・ホレンダー。だがその歌を歌う肝心のヒロインには、『メトロポリス』そのほかで有名なブリギッテ・ヘルムの出演が無理だということで、まったく無名のマレーネ・ディートリヒというのは、本当はおかしい。マゼッパ役に起用されたハンス・アルバースにしても、映画俳優としては未知数である。つまり起死回生をねらって多額の金を投じた企画にしては、リスクの大きすぎる配役なのである。たとえウーファが期待をかけたのは、押しも押されもせぬ大名優エーミール・ヤニングスだったとしても、そしてウーファがマレーネ・ディートリヒと次の契約をしなかったように、本来ヒロインをそれほど重視していなかったのだとしても、それでは監督のスタンバーグの思惑との違いが大きすぎる。さらにもっと奇妙なのは、原作が札付の進歩的風刺作家ハインリヒ・マンの『ウンラート教授』だということである。もちろんフーゲンベルグが支配するウーファが、いかに商売のためとはいえ、ハインリヒ・マンの小説の映画化を企画することなど、あり得ないことだった。その証拠にでき上がった映画は、ハインリヒ・マンが怒ったように、原作の『ウンラート教授』とは似ても似つかぬ『嘆きの天使』だった。第一、社会風刺の作家としてのハインリヒ・マンを取り上げるつもりなら、ヴォルフガング・シュタウテが1951年に撮った『臣下』の方が本筋である。したがって俗物のラート教授が安いキャバレーの歌姫のために身を持ち崩すなどという物語を原作にし、しかもそれをウーファの経営人も満足するような、サディスティックな新しい「性」を描く映画に作り替えるのなら、何もわざわざ札付のハインリヒ・マンの作品を取り上げ得る必要はなかったはずである。
つまりこの映画はおよそちぐはぐな、矛盾した思惑の錯綜した同床異夢から生まれた、ハプニングのような作品なのである。ハプニングは大名優エーミール・ヤニングスの自信たっぷりの重厚な演技が、名演技であるにもかかわらず、すでに時代遅れであったために、マレーネ・ディートリヒの「足」に食われてしまい、だれ一人思いがけなかった「ディートリヒ伝説」を成立させるだしになってしまったことで、完成した。それゆえこの映画は、監督のスタンバーグを含めて、関係者すべての思惑を超えた、「時代」そのものの所産である。バルバーラ・ローガルはこう書いている。「スタンバーグの決定は、当時のドイツ・トーキー映画の状況から切り離して見ることはできない。それはトーキー映画が生まれた時期のブルジョア映画産業によって操作された大衆の趣味に対するある種の譲歩を示している。その結果行われた物語の一面かは、小説の社会批判的な幅を無力にしている」。しかしその結果として本来映画化の難しい小説が、時代を象徴する「所産」として映像化されたのである。
そこにこの映画が、ブレヒトの『三文オペラ』と同じように、矛盾した時代的意味を持つ理由がある。一方でそれはハインリヒ・マンの社会批判を骨抜きにし、「内容空疎な見せかけの虚飾」によって「実質の無さ」を覆い隠したはったりと評価された。他方でそれは「当時の現実の下にある地層を暴き出した<時代の雰囲気>そのものの映像化と評価された。S・クラカウアーは、この映画が封切られた1930年に書いた批評では前者の立場をとり、『カリガリからヒットラーまで』では後者の立場をとっている。彼の評価の揺れは、まさにこの映画の「いかがわしい真正性」の持つ新しい「質」を証明している。それを象徴しているのが、主題歌『わたしはイカすローラ』と、『わたしは頭の先から足の先まで恋そのもの』のメロディであり、今日まで続いている「ディートリヒ伝説」である。
それゆえ「ディートリヒ伝説」は、単に彼女の裸の足の魅力によって生じたものではない。またその魅力も単に時代にマッチした新しい型のヴァンプと言うことから生じたものではない。スタンバーグが彼女を連れてアメリカで撮った第二作『モロッコ』(1930年)の幕切れは、大金持ちの男を袖にし、しがない外人舞台の兵士の後を追って、灼熱の砂漠の中へ裸足で消えていく女の姿である。ディートリヒ伝説を決定的にしたこの作品を考えても、サディズム的ヴァンプ性と、その背後に潜む純粋な魂との奇妙な共存こそ、彼女の体現する人物像の新しさである。『ワイマール文化』の著者ピーター・ゲイは「ワイマール精神をはっきり現わしたもの」として、「カリガリ」、グロピウスの建築、カンディンスキーの抽象画、グロスの風刺画と並べて「マレーネ・ディートリヒの足」を挙げ、そうした見方に批判的なウォルター・ラカーすら「ワイマル時代は、思想家達の時代であったと同時に、フリッツ・ラング、マルレーネ・ディートリヒ、リヒャルト・タウバーのような人びとの時代であった」と述べている。「ディートリヒ伝説」は、彼女の演じた人物像がこうした時代的意味を担うものと受け取られていることで強化されているが、それもこの人物像に内包する異質なものの奇妙な共存に対して、時代が共感したればこそである。それゆえ、「伝説」がなお持続しているということは、そうしたアンビバレントな女性像を魅力的と感ずる基盤が、今日でも以前として持続していることを示すものであろう。
ドイツ1919〜1931映画回顧展(1995年11月)