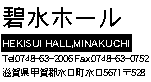ドイツ1919〜1931映画回顧展(1995年11月)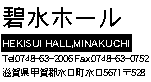
■フォーゲルエード城■■■■
Schloss Vogel單
1921年/白黒サイレント/58分
スライド日本語字幕付
脚本:カール・マイヤー、(ルードルフ・シュトラッツの同名小説による)
撮影:フリッツ・アルノー・ヴァーグナー、ラースロ・シェーファー
美術:ヘルマン・ヴェルム
製作:ウーコ映画株式会社
監督:フリードリヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ
出演:パウル・ハルトマン(ペーター・パウル・エッチュ伯爵)、オルガ・チェホヴァ(ザッフェルシュテット男爵夫人)、パウル・ビルト(ザッフェルシュテット男爵)、アルノルト・コルフ(フォーゲルエード城の城主フォン・フォーゲルシュライ)、ルル・キューゼル・コルフ(ツェンタ、彼の妻)、ロタール・メーネルト(ヨハン・エッチュ伯爵)、ヘルマン・ヴァレンティン(退職地方裁判所判事)、ユーリウス・ファルケンシュタイン(気の小さい紳士)、ゲオルク・ツァヴァツキー(見習いコック)、ローベルト・レフラー(家令)、ヴィクトル・ブリュートナー(ファラムント神父)、ヴァルター・クルト・クレー(召使い)、ローニ・ネスト(子供)
【あらすじ】
フォーゲルエード城で狩猟の会が催される。だが雨の多い10月の天気のため、まだ遠出ができない。思い駆けず、ヨハン・エッチュ伯爵が仕事に姿を現わす。ザッフェルシュテット男爵夫人も夫と一緒に来ることになっているので、城主は伯爵に出発するようすすめてみるが、無駄である。男爵夫人は、エッチュ伯爵の、殺された兄弟の夫人だったのである。エッチュは、自分の兄弟を殺した疑いをかけられている。出会うのを避けるために、男爵夫人は到着後、すぐにまた出発しようとする。彼女の最初の夫の遠い縁者であるファラムント神父も来ることを聞いて初めて、彼女は留まる決心をする。神父を知っている者は誰もいない。真相を究明しようと思っているエッチュは、ファラムントに変装して現われる。男爵夫人は彼に告解しようとする。彼女は彼にまず、ペーター・パウルとの結婚生活について語る。パウルは、ある旅行から帰って来ると、まったく人が変わってしまっていた。彼は自分の全財産を貧しい人々に分配しようとし、そのため彼の兄弟と口論になった。ここで彼女は話しを中断し、翌日になってから先を話そうとする。夜、彼女が神父を呼ばせると、彼は姿を消している。狩猟の一行が出発する際、彼女はエッチュ伯爵を責めて、彼が兄弟のパウルを殺したと言う。退職地方裁判所判事は、ファラムント神父が姿を消したことを、エッチュ伯爵と関係があるとする。しかし神父が再び姿を現わし、男爵夫人は告解を続ける。それを聞くと神父は仮装を取って、エッチュ伯爵としての正体を現わし、男爵夫人が偽のファラムント神父である彼に打ち明けたことを、男爵に告げる。男爵は必ずしも彼女が無関係とはいえない不幸な資産状況のために、ペーター・パウル伯爵を射殺したのだった。男爵は自殺する。そのとき本当のファラムント神父が、ローマから到着する。
【解説】
この作品は当時ドイツで広く読まれた「ベルリナー・イルストリールテ」誌に掲載された後、「ウルシュタイン・ブック」として巨大な部数を売った、ルードルフ・シュトラッツの通俗小説を映画化したものである。ということはムルナウがその精巧な映像言語によって、彼自信の里程標でもあり、映画史上の古典の位置を占めるような作品を作るための原作としては、いささか貧弱な作品だったということである。
しかし『ノスフェラトゥ』を作ることになるムルナウは、このさしたることもないスリラー小説から、「不気味なもの」が漂ってくる雰囲気を汲み取ることに成功している。それにしてもムルナウは、この映画をわずか16日間で撮り上げたのだから驚きである。シャルル・ジャミューはこの映画について、こう書いている。「この作品は、ムルナウ監督が、まったく外面的なファンタジー(『ジキル博士とハイド氏』)、自然主義的なドラマ(『せむしと踊り子』)、探偵映画(『夕方…夜…朝』)そして農民風室内劇(『マリッツァ』)といった気楽な因習的作風に背を向けた、最初の映画であるように見える。そのためには現在へ向けての転換がある。時は1911年である。ムルナウの世界が形を成してきた。ドイツの反革命によって動揺させられたこのサロンの屈折した雰囲気は、私にはまったく別の対決の口実となっているように思える。装置は、情熱を抑えられた諸人物が動き回る心象風景の、モデルとしての役を果たしている。」。実際ヘルマン・ヴァルムの作成したフォーゲルエード城のセットは、雰囲気を出すのに大変役立っている。
更にカール・マイヤーのシナリオも、そうした気分をあらかじめ細部に至るまで定着させている。例えば「告白」というシーンは、その典型である。ヴィリー・ハースは「フィルム・クリール」誌に、こう書いている。「この映画には<告白>というタイトルのシーンがある(巨大な、天井の高いホールに、愛のために人殺しをした殺人者が、彼の恋人と一緒にいる。2人は全く動かない。まるで彫像のように)…映画が始まって以来、このような場面が示されたことは稀である」。
「さらにいえば、ムルナウの様式の中で独特なのは、本来の行為そのものとはあまりつながりを持っていないグロテスクなシーンがところどころに挿入されていることである。城の台所でボーイはつまみ食いをしたために、コックに平手打ちをくらう。するとボーイは、その夜、自分が台所にいてファラムント神父から、つまみ食いをするための鍵をもらい、鍵の中に指を入れるたびにコックの頬をひっぱたく、という夢を見る。もうひとつのシーンでは、けづめのついた手が窓から部屋に入ってきて、自分を雨の中に連れ出そうとする悪夢に悩まされる城主の場合である。これらのシーンをフロイディズムの影響と指摘するのは易しいが、ムルナウの場合、ただそれだけでないのは、それらのグロテスクなシーンがいわゆる現実の時間とないまぜになってしまって、ひとつの世界を作り出してしまう天与の才能のあることである」(『ドイツ表現派映画回顧上映第4・5期パンフレット』、6ページ)。
ドイツ1919〜1931映画回顧展(1995年11月)