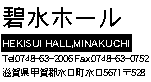ドイツ1919~1931映画回顧展(1995年11月)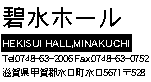
■吸血鬼ノスフェラトゥ■■■
Nosferatu
1921年/白黒サイレント/65分
スライド日本語字幕付
脚本:ヘンリック・ガレーン(ブラム・ストーカーーの小説『ドラキュラ』による)
撮影:フリッツ・アルノー・ヴァーグナー、ギュンター・グランプフ
美術:アルビン・グラウ
製作:デークラ・ビオスコープ社
監督:フリードリヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ
出演:マックス・シュレック(ノスフェラトゥと称されるオルロック伯爵)、グスタフ・フォン・ヴァンゲンハイム(トーマス・フッター)、グレタ・シュレーダー(エレン、彼の妻)、ヨーン・ゴットウト(バルヴァー教授)、グスタフ・ボッツ(町医ジーファース教授)、アレクサンダー・グラーナハ(家屋周旋屋クノック)、ゲオルク・H・シュネル(ハーリング)、ルート・ランツホフ(アニー、彼の妻)、ヴォルフガング・ハインツ(水夫1)、アルベルト・ヴェノール(水夫2)、ギド・ヘルツフェルト(亭主)、ハーディ・フォン・フランソワ(病院医師)
映画の英語版では、登場人物に対して、ストーカーの本に由来する次のような名前がつけられている。
オルロック伯爵=ドラキュラ伯爵、トーマス・フッター=ジョナサン・ハーカー、エレン=ニーナ、ハルヴァー教授=フォン・ヘルジング、クノック=レンフィールド、ハーリング=ウェストレンカ、アニー=ルシー
【あらすじ】
ブレーメンで妻エレンと幸福な結婚生活を送っているフッターは、家屋周旋屋クノックの従業員である。彼はある日、ノスフェラトゥと称される神秘的なオルロック伯爵のところへ、売買契約を結ぶために派遣される。すでに旅の途中で、フッターは奇妙な幽霊の出現に出会う。トランシルヴァニアの住民たちはこの旅行者に、「幻の国」に用心するよう警告する。フッターはそれを気にかけず、城に到着した後、伯爵を探して神秘的な城中を歩き回る。オルロックは夜の時間に彼を迎え、売買契約にサインする。翌朝フッターは、自分の首に2つの赤い傷跡を発見する。次の夜オルロックは、その若い男に近づいて、血を吸おうとする。悪夢にうなされてエレンが、ブレーメンで目を覚ます。彼女は夫の名前を呼ぶ。彼女の叫び声は吸血鬼ノスフェラトゥに迫り、彼は自分の犠牲者を手離すほかはない。ノスフェラトゥはけがれた土を一杯に詰めた棺を持って、城を去る。フッターは逃げる。慈悲深い人達がこの疲れ果てた男を見つけ、看病して元気にしてやる。ノスフェラトゥはフッターより先に、ブレーメンへ向って急いだ。彼が姿を現わす所には、ペストが広まる。不気味な積み荷を乗せた帆船上では、水夫が次々に死ぬ。ブレーメンに着いた時、死んだ船長がかじにしばりつけられ、首に赤い傷跡をつけられた姿で発見される。医者は、ペストが町中に広まっているのを確認する。フッターもブレーメンに着いた。エレンは彼の手荷物の中に吸血鬼の本を見つけ、ことの次第を感じ取る。その本は、清らかな心を持った女性なら吸血鬼を防げて、夜明け前にけがれた土の棺に戻れないようにすることができると、述べている。ノスフェラトゥはエレンの窓に向かい合った家に入った。エレンはこの怪物を招待して自分の所へ来させ、彼に首を差し出す。朝日がさして吸血鬼をくずれさせ、塵に戻す。医者を連れてエレンの所へ急いで来たフッターは、瀕死の状態にある妻を見つける。怪物の仲間のクノックは、親分と同じ時に精神病院で死ぬ。
【解説】
ブラム・ストーカーの小説「吸血鬼ドラキュラ」を下敷きに、『巨人ゴーレム』や『プラーグの大学生』、『妖花アラウネ』といった、ドイツ版怪奇幻想映画の傑作のシナリオや監督に関与したヘンリック・ガレーンがシナリオを書いたこの映画は、まさにアングロ・サクソン系の恐怖文学とドイツ系の幻想文学の成果を統一して、「映画」という新しいジャンルに移し、映画という媒体がそうした性質を表現するのに極めて適していることを示して、今日までつながる世界の怪奇幻想映画の源流となった記念すべき作品である。同時にそれはムルナウが、20年代ドイツ・サイレント映画の巨匠の一人にのし上がる過程で『フォーゲルエード城』に続いて発表した、彼としても重要な位置を占める作品である。
『ドラキュラ』だけでなく一般に吸血鬼は、主としてイギリス・アメリカ映画の、お気に入りのテーマとなり、玉石混淆ほとんど枚挙に暇がないほどの盛況振りとなったが、果たしてこのムルナウの『ノスフェラトゥ』をしのぐ作品が生まれたかどうかは疑わしい。ヴェルナー・ヘルツォーク監督による最近の再映画化も、ムルナウの傑作を忠実になぞった作品である。もっとも英米系の「吸血鬼」映画には、ほとんどマニア的なファンが多いので、こうした見解は与しない意見の方が強いかもしれない。たとえば季刊「映画宝庫」No.11『ドラキュラ雑学写真辞典』などは、そうした傾向を代表している。ただ通俗的な吸血鬼映画が、イギリス・アメリカで大衆の圧倒的支持を受けたことは確かである。本当はドイツ系、英米系と分けずに、少なくとも両者を統一して、ヨーロッパ的視野で、「吸血鬼」物の映画が持つ意味を問うことが望ましいし、今後の課題であろう。
ドイツ映画の黎明期にいちはやく「キーノー・ブック」を編纂して、映画の未来を示唆したクルト・ピント蓜スはこの映画の幻想の美を賞賛して、ムルナウを3乃至4人の力量ある映画監督の一人に数えた。「コントラストとして抒情的な要素と春の朝のような情緒が、きわめて晴朗な印象を与える。ムルナウはこの映画で若い人々だけをつかった。それが彼の映画に柔らかさと抒情性を与えている」。
ロッテ・アイスナーは「デモーニッシュなスクリーン」において、ムルナウについてこう述べている。「ドイツ最大の映画監督フリードリヒ・ヴィルヘルム・ムルナウの映画の構成は、決して単なる装飾的様式化を意図したものではない。彼はドイツ映画全体の中で、最も圧倒的で、最も痛烈なイメージを創造した人物である。彼は芸術史の訓練も受けていた。フリッツ・ラングが有名な絵を忠実に再生しようと意図したのに対し、ムルナウはそうした絵について自分が持っている記憶を彫琢し、それを自分個人のヴィジョンに変換する。ムルナウは自分自身から逃げようとしていたので、フリッツ・ラングのように、芸術的な一貫性によって自分自身を表現することはしなかった。しかし彼の映画のすべては、彼の内的コンプレックスの記号となっている。つまり彼の映画は、彼が絶望的に無縁な存在に留まっている世界に対しての、彼自身の内部での戦いの記号となっている。最後の映画『タブウ』においてだけ、彼は平和と若干の幸福を見い出したように見える」。
【作品評】
ルードルフ・クルツ『表現主義と映画』(1926年)から。「…ヤニングスをつかった『最後の人』で、はっきりと様式化された傑作を創造したムルナウは、ことによるとまだ意識的な表現主義ではないが、その形式に近づいているように見える諸要素によって、彼の吸血鬼映画『ノスフェラトゥ』の中で、心の雰囲気をかもし出す不気味な印象を作り出そうと試みた。ヘンリック・ガレーンがしっかりしたシナリオで構成したこの恐怖に満ちた冒険においては、ねずみやペスト船や、吸血鬼どもや暗い丸天井、稲妻のように走る馬に引かれた黒い荷馬車などによって生み出される重なりあった幻想が、相互に作用しあってデモーニッシュな効果を上げているが、それは始めから自然主義的描写を避けていた。ムルナウは非現実的性格を強調し、趣のあるヴィジョンを作ることを目指して演出した。そして自然のままのフォルムでは与えることのできない、あの恐怖の効果を達成した…」。
1922年9月11日の『フィルム・クリール』。「…彼の幻想的なノスフェラトゥ映画は名人芸によってセンセーションを巻き起こした。その名人芸によってここでは、生きた映像の無言の言語が、その迫力から誰も逃れることのできないような力を振るっていた…。どんな場合でもムルナウの映画では、われわれは極めて強烈な個性に関わることになる。だからと言って、目的のためには手段を選ばぬ野心家と関わっているのではない。まったく明白に座礁してしまい、まともに先へ進めなくなっているドイツ映画を、どうやったら救うことができるかについて頭を痛めている、思案する人と関わっているのである。彼は一つならぬ点で、われわれの映画の世界の枠からはみ出す。映画人の間で薄い金髪のフリースランド人の姿に出会うことが、すでに異例である。彼はいわば『映画の国の寡黙の人』の1人に数えることができる(フリッツ・オリムスキー)」。
ドイツ1919~1931映画回顧展(1995年11月)