H.V.S通信 vol.48 2001年(平成13年)9月
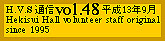 home●<>
home●<>|
「短所を直すより長所を伸ばせ」「 誉めて伸ばせ」という教育論が幅を利かせる時代、まさにそのど真ん中に育った私こと井上が、この世のさまざまな事象に対してホメまくる「礼賛シリーズ」! 〜ライブで感じられる演奏技術の ものすごさをほめる!〜 1回目はここ水口に二度目の来町を果たしたザ・ベンチャーズ!。ベンチャーズといえば実に来日回数40回を超えるスーパーバンド。とはいえスタン・ハンセン、バースなどと並ぶ「スーパースターIN JAPAN(つまり本国では無名ということですね)」の代名詞ともいえる存在でもありましょう。事実水口のコンサート、私も若い頃に彼らに夢中になった父への親孝行として同行しただけでした。取れた席は前から3列目、これなら父もご満悦であろうと安心して開演を迎えたのでした。しかし・・・ 始まった途端、私の目は釘付け!ベースのボブさんの前にいたんですが、16ビートなど屁でもないとばかりにブンブン弾きまくる!もともと彼は大ヒット曲『急がば廻れ(Walk don't Run)』でギターを弾いていた人で、リードべースといえる演奏も納得。 「テケテケさん」ことドンさんは、完璧な「リズム」ギター。うれしいのはそのギターの音がはっきり聞き取れ、そしてそれがベンチャーズの音の要になっていること。ツインリードなんてこざかしいことしない!そしてテケテケの大音量、こりゃパンクだ! リードを担当するジェリーさんはさりげない南部タッチのフレーズが素晴らしい。今回は1930年代のジャグバンド(ビンや洗濯板などを使って演奏した初期のジャズ)の名曲『アラバマ・ジュビリー』でブルージーだが軽快なギターをかましてくれました。 ドラムのリオンさんはメンバーだった父メル・テイラーさんの息子さん。これまた無駄はないが鋭いドラミングで聴かせる。フリースタイルとリズムキープを同時進行させる驚異のドラミング技術を持った父メルさんの域に近づくのももうすぐでしょう。 初来日からお約束になっているアンコール曲『キャラバン』ではまさにこの4人のプレーが火花を散らします。それぞれがすべてリード楽器のように激しく演奏していながら、同時にどの楽器も突出せずひとつの曲を作り上げているのです。音のかたまりだがひとつひとつの楽器もちゃんと聞き取れる、どれかの楽器の休符には別の楽器の音符がからみつく、というロックバンド(ギター、ベース、ドラム)のアンサンブルの完成形といえる演奏を聞かせてくれました。唖然と言うほかない状態で私は彼らの演奏を見ていたのでした。 まさに「ビートルズ前夜」だった こりゃ大変だ、ということでさっそく父が録画していた5年前のライブと近所の貸しビデオ屋さんにあった『愛すべき侵略者たち〜ベンチャーズ1966』を見てみました。そして改めてものすごい演奏技術に驚いたのです。 特に『愛すべき侵略者たち』。この時のベンチャーズはまさに全盛期。エフェクターも何もない時代だというのに、伝説のギタリスト、ノーキー・エドワーズさんのギターの音色が刻々と変化するのです。その中でも基本はおそろしいファズ(歪み)のかかったぶっとい音。ファズなんて翌年ジミヘンが多用するまで一般的には知られていないはず。この年来日したビートルズの演奏と見比べてみると、インストグループとボーカルグループの差やビートルズのやる気のなさを差し引いても演奏力の差は歴然。ビートルズが『デイ・トリッパー』でレコード盤に記録した実験的ファズサウンドを、ベンチャーズは笑顔を振りまきながらライブで演奏しているのです! 雑誌『レコードコレクターズ』によると彼らは本国アメリカでもレコード売上も高く(1960〜2000で通算売上8位!)、先鋭的なサウンドづくりで多くのミュージシャンから(スティーリーダンからラモーンズまで!)尊敬を受けているミュージシャンでもあることがわかりました。 日本だけではない! 彼らの活動開始は1962年。この時期はまさに「ビートルズ前夜」。当時のヒット曲はニール・セダカやコニー・フランシスなどのポップス勢が強い時代。ディランとビーチボーイズはいますが、まだ海のものとも山のものともわからん存在だったはず。サウンド面ではフィル・スペクターの「ウォール・オブ・サウンド」が花盛り。ピアノとコーラスが中心で、ストリングスがあたりまえのように演奏に使われていた曲が多い。それらの曲とベンチャーズの曲を比べてみると、ギター、ベース、ドラム、たまにキーボードという最小限のロックアンサンブルで勝負していたことに驚きます。 「俺もやってみよう」という熱意が ロックという音楽を前進させる 当時のロック少年達にとって「俺もやってみよう」と思える音楽はベンチャーズのような曲のみだったはずです。この「俺もやってみよう」という熱意がロックという音楽を前進させることを考えると、この時代ロックを前進させていたのは、きっとベンチャーズのようなロックインストバンドだけだったのでしょう。 そんな中でベンチャーズはその卓越した演奏技術をもって『急がば廻れ』『ハワイ5-0』などの全米大ヒットを飛ばしただけでなく、他の人の曲もどんどん取り上げ、料理していった。多くのロックファン(私も!)がビートルズから『ロックンロールミュージック』や『のっぽのサリー』を知ったように、ベンチャーズから『ワイプアウト』や『パイプライン』を知った。初期ビートルズの魅力のひとつが埋もれていたロックの名曲を原曲以上のパワーで表現したことにあるのなら、ベンチャーズはまさにそれ一点で勝負した頑固オヤジ的なバンドだった。こりゃ本物です。しかもメンバーはほぼ不動(ギターのノーキーさんは今もちょこちょこ客演)。叩き上げの実力があるのです。 〜徹底した現場主義の ミュージシャンシップをホメる!〜 そしてなんと言ってもベンチャーズの偉大なところは、毎年ライブをする、という姿勢です。『レコードコレクターズ』の評価を考えると、ロック界の中で彼らは『大御所』としてふんぞり返ってもいい位置にいます。お金に困る人たちでもありません。 しかし毎年やってきてくれる。それはライブという“現場”にこだわっていることの証明です。現場というのは生ものですから、様々な困難やトラブルに見舞われます。客入りの悪い日も、反応がさっぱりな日もあるはずです。しかし彼らは今も現役としての誇りを持って活動を続ける。私がベンチャーズの偉大さを感じるのはここです。常に現役として“現場”に立ち続ける姿勢に圧倒的な信頼感を感じます。 ロックも年月を重ね、成熟の時を迎えています。オリジナルな新作を発表することが活動のすべてではなくなりました。過去の作品を「アメリカ国境に住む貧しい人々」というテーマで再構成してライブを行ったスプリングスティーン、毎日のように演奏曲目を変え観客を驚かせたり迷わせながら「ネバーエンディングツアー」を続けるボブ・ディラン、名作『ペットサウンズ』の完全再現ライブに取り組むブライアン・ウィルソンなど、「パフォーマー」としての魅力で活躍する人たちが出てくるようになりました。 ベンチャーズは『十番街の殺人』や『ダイヤモンド・ヘッド』など10曲以上はある定番曲を確実に披露することで、観客の8割を占める「なつかし派」の人々を満足させつつ、その間に「おぉ!」と思わせる選曲やプレイをはさんで、残り2割の音楽マニアやギターフリークなどの度肝を抜いてきます。彼らはどちらをも満足させる傑出したパフォーマーであるといえるでしょう。 このような人たちですから演奏が単純に上手いだけではありません。上手いんだけど上手さで勝負しない。「間」とか「息づかい」とかが音の後ろに張り付いている。それは毎日のようにライブという現場を経験しておかなければ身に付かないものです。以前クラシックのコンサートで、最初に見た四重奏が「上手いんだけど退屈」と感じ、次に世界的演奏家を見たら「あ、人間が弾いている!」という感動があったことがありました。この「人間が弾いている!」と感じさせることが一流中の一流の音楽の条件だと思います。その点でもベンチャーズは本物です。私でも弾ける『ダイヤモンド・ヘッド』、でも全く同じメロディーを弾いていてもサウンドは天と地ほどちがう。これぞ本物の魅力です。 〜今からでも遅くない! でも時間もないぞ(失礼)〜 というように、ベンチャーズはまさに真のロックバンド。懐メロバンドではあるし、現在日本が活動拠点になっているのも事実。しかし、それは一部に過ぎません。音楽の腕に覚えのある人、一度見に行ってみなさい!恐ろしいまでの「不朽の音楽」にきっと打ちのめされるはず。 彼らを毎年見られることは幸せ以外の何者でもない!でも平均年齢は60を越えているし、この幸せは長くは続かないのも現実。来年はどこに来てくれるんだろう。もう一度3列目より前で改めてベンチャーズが見たい!1列目だとピックがもらえる可能性大!あのコンサートを見なかった人、特に「懐かしバンドでしょ?」と思っていた若い奴ら・・・後悔せい! (井上陽平・HVS) |
う な り ゃ 何 で も 褒 め て や る ! 井 上 陽 平 の 礼 賛 シ リ | ズ ザ ・ ベ ン チ ャ | ズ |