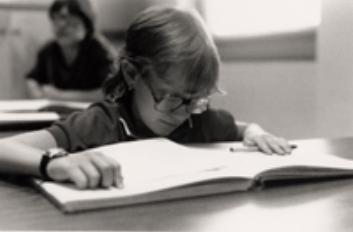HVS通信 vol.71
2004年(平成16年)8月
夏の音展(かずろう・取材/上村秀裕)...1
知らない世界へ(minami)....2
近江八幡に新しいギャラリーが(上村秀裕)...2
フレデリック・ワイズマン映画祭続報(上村秀裕)...3
「ガムランでミュージカル・・・」(中村道男)...4
サザナミ記念アンサンブル定期演奏会4°2004
旭堂南湖さんが地元甲南町で講演
編集・発行
碧水ホールボランティアスタッフ
滋賀県甲賀郡水口町水口5671
郵便番号 528-0005
電話 0748-63-2006
ファックス 0748-63-0752
e-mail michio@jungle.or.jp
ホームページ http://www.jungle.or.jp/hvs/
碧水ホールの公式ホームページ
http://www.town.minakuchi.siga.jp/hekisuihall/
| 発売中 |
2004年9月11日土曜日
中川真・企画監修
演奏 マルガサリ+野村誠他
第1部 午後2時 古典曲・舞踊
第2部 午後5時 楽舞劇「桃太郎」第3、4場
通し券 前売り2000円 全席自由

「桃太郎」第3場から 団子三姉妹
ガムランワークショップ
| 申込受付中 |
コンサートに併せて、9月11日(土)午前10時から、初めての人向け演奏体験ワークショップが開かれます。
2004-8-21(sat)
毎年8月に開催される「夏の音展」の仕掛人、「花屋かずろう王国」の店主かずろう さんにインタビューしてみました。
■「夏の音展」というライブイベントを思いついた発端は?
自分自身音楽をやってまして、毎年一本大きめの自主企画ライブを打つんですが、 もちろんそれはバンドメンバーのみで実現出来るものではありません。とくにイベン トが大きくなればなるほど企画提案者やスタッフも沢山いります。ありがたいことに 内のバンドは恵まれてて毎回精力的に動いてくれるスタッフがいてくれます。みんな そうなんですがまるで自分のことのようにたのしそうに働いてくれるんです。あると きそんなスタッフの一人に「君も一度演奏する側になってみたら?」と声をかけたん です。とても気軽にね、するとその反応がすごくてね、ときめき感というかドキドキ 感みたいなものがその人から伝わってね。「僕もでていいの?」というような。その 時ですね、これっておもしろいなとひらめいたのはね。
■今年で6年目ですが、年々出演希望者が増えていますね。
イベンターという立場ですと本当にうれしいことですね。夏音自体に力があるとい うことですから。今まで人前で演奏したことがない人が最初にステージに立つ時って むちゃくちゃでっかい緊張感と闘うわけですよ。上手い下手関係なしにすごいエネル ギーがオーディエンスに届きます。それを感じた人が「僕も出たいな」って思う、そ の連続ですかね。ほんと嬉しいです。
■初めて人前で歌おうとする人達に、かずろうさんは、どんな言葉をかけてあげるんですか?
先ずは「どう?」って軽薄に。そんで例えば「途中で間違っても絶対止まるな」とも。「 取り繕わないでそのままでどうどうとやりな!」って言いますね。プロじゃないし、し かも初心者なら下手に決まってるしね。ただ下手なりのかっこよさが必ずありますか ら。技術や確実性から入って欲しくないんです。音楽は自由じゃないといけないと思 う。だからね、上手くまとめようなんてする必要はないんです。つまらないから。僕 も実際そうで、ライブ来てくれた人は分かるかもしれませんけど、かなりいい加減 です。イケイケでやってますよ。毎回ね。それでお金頂いてる。
■「夏の音展」には毎年テーマがありますが、今年のテーマは?
毎年適当なんですよ、実は。けど今年は特別、砂漠の国に気持ちが行ってまして。 同胞が危険地帯で働いてる。砂漠の国の人々は生活エリアにいつも危険がある。水口 にいたんでは到底考えられない、想像も出来ない状況下でみなさん生きてる。しかし 僕は使命感とか正義感とかでそこには行けないんです。そんな勇気はないし。恐いし 実際。いいわけがましいけど、ここ水口に居ながらにして何か出来ると思うんですよ。 小さなギターの音が大きなバイブレーションに変わっていくイメージはいつもしてる んです。だから今回は「砂漠には行かない 僕は碧水ホールに行く」と。
■最後に、読者の皆様へ一言どうぞ。
気軽な思いつきから始まった「夏の音展」ですが、代表の自分が言うのもなんですが、 とても素敵な音的イベントだと思います。お時間合えば是非お越し頂きたいです。当 日、飲食のお店もロビーに出ますしぶらっと散歩がてら来て頂ければ嬉しいですね。 今年は暑くなりそうだしビールはかなりいけるでしょうしね。
■ありがとうございました。今年の「夏の音展」も、どんな音との出合いがあるのか、楽しみにしています。
|
夏の音展 開催日時 2004-8-21(sat) 多分2:00pm開演 会 場 碧水ホール・ロビー 入 場 料 300円 出演者募集中です。若干名(グループ) 問い合わせ先 office夏の音展/cocoloRcompany TEL.0748-63-3362 cocolo@mcv.zaq.ne.jp http://www.mcv.zaq.ne.jp/kazuroo/ |
(取材/上村秀裕/碧水ホール学芸員)
(kanae・HVS)

原稿をお寄せください。
自分の活動やイベントの紹介も可。
HVS通信はためぐち感覚、投稿はファックス、
E-メール、チラシ裏の手書きやフロッピーを郵送、
どれでも結構です。
若干の編集を加えてインターネットホームページにも
掲出されます。
「そうとうハマってるな、こいつ。」と思われるとちょっと困るのだがぼちぼちなのである。
今回ハマった友人は「冬にはミニョン巻きをしよう。」と言う。ミニョン巻きとはマフラーの巻き方である。縦にしたら中尾彬巻きなのだが。日本ではどうだったのか韓国ではこのミニョン巻きなどファッションも流行ったのだとか。そういえば私はユジンのコートを毎回見るのが楽しみやったなあ。そうそう、あと韓国の人ってみんな鼻の穴が異様にキレイ。これもひょっとしてキムチ効果というやつかしらん。
冬ソナを見るのは二度目だが、今回はそのあとにハングル講座の番組があったりしたので+αの面白さがある。この前言っていたのは「韓国人は愛の定義を下してから恋に落ちる。」「韓国人は人生論をたたかわせるのが好き。」というもの。ハッキリ言って苦手なのである、こういうのは。あたしゃ韓国人に生まれなくてよかったよ、と思った。哲学なんてなんの興味もない。「人生とは何か?人は何のために生まれてきたのか?」なんてカンベンしてほしい。
でも、番組ではこうも言っていた。「人生論が語れないのはまだ子供だ。人生論が語れるようになって大人(と韓国では考えられている)。」
「ふうーん。」と思った。毛嫌いしていたことが少し心の中に入って来た。
とにかく、人生論がきちんと語れたらいいなと思う。大人になって急に口ベタになった私はホントそう思う。キライだから語らないのか、ひょっとして語れないから嫌いなのか分からなくなってきた。でも、そうやって触れられなかったものに少しずつ触れられてきたらいいな、とも思う。
そうそう、この春死ぬほどキライだったカエルに近づくことができた。これって違う?
(kanae・HVS)
新しいギャラリーが
誕生
ボーダレス・アー トギャラリーNO-MA

(文・写真/上村秀裕/碧水ホール学芸員)
滋賀県にも7月3日、近江 八幡市の旧市街にある町屋がギャラリーとしてオープンした。名前はボーダレス・アー トギャラリーNO-MA。NO-MAとは、家主だった野間氏のノマだが、ニューヨーク近代美 術館の略称MOMAにも似ている。もともとは個人の住宅で、築70年にして現代の手が加 えられ、公共空間として存命していく。
八幡堀を再生させた近江八幡には、現代の息を吸って新たな価値を産む建物が少な く無い。このNO-MAの付近でも、酒造会社の酒蔵が飲食スペースとともにライブス ペースになった酒游舘という先進例があるし、ジャズが聴ける喫茶店、ボーリズ 建築の公共スペース、かわらミュージアム等々、これらがゆっくり気ままに散策を楽 しめる行動範囲として点在しているのだ。
さて、NO-MAのオープニングを飾る企画展「私あるいは私〜静かなる燃焼系〜」に ふれよう。この企画展には、5人の作家が出品しているが、時代、ジャンルを超えて、 まさにボーダレスな作品が揃っている。
オープン前日の内覧会では、出品作家の中か ら森村泰昌と伊藤喜彦が出席しており、お二人のスピーチも披露された。会場で、独 り言を話しながらうろうろしているおじさんが、どこかで見た人だと気にはなってい たのだが、それが信楽青年寮で暮らしている作家の伊藤喜彦その人だと気付くには、 そう時間はかからなかった。彼のスピーチがとてもすばらしくその話しぶりを聴い て、佐藤真監督作『まひるのほし』に出ていた人だとすぐにわかったからだ。映画 『まひるのほし』を見た人なら、「なさけない、なさけない」を連発する姿とともに、 彼の造形作品を思い出すに違いない。1934年生まれというから今年70歳を迎える伊藤。 映画の中以上に、若々しくて楽しい人だ。
この展覧会最大の発見は、岩崎司という未知のアーティストだった。市会議員も務 めたという彼は、現在、精神を病んで入院生活をおくっているという。その特別な空間 で得られる素材は限られており、たとえば新聞折り込みの広告を、作品のための額縁 に使っている。その額縁に囲われた作品には、絵画とともに祈りともとれるような言 葉がちりばめられている。達筆だ。
岩崎司の来館も計画されていたが、とても施設の 外へ出られる状態ではないとのドクターストップがあり、実現しなかったと、主催者 からレセプションのときに報告があった。畳の部屋に展示された岩崎の作品は、あぐ らをかいて、ゆっくり眺められるようになっている。
この展覧会は、期間中に、ワークショップ、コンサート、岩下徹のダンスなどのラ イブイベントも計画されている。展覧会は9月20日(祝・月)まで。
展覧会のお問い合わせはTEL.0748-36-5018
http://www.hukusi-shiga.net/jigyoudan/
(文・写真/上村秀裕/碧水ホール学芸員)