
撮影:中谷賢一郎(HVS) 2002.10.12 セタンタ来日公演 碧水ホール
ひさびさのアイルランド音楽、うちの奥方と2才半のこどもも碧水ホールに初来館して、一家総出で楽しませていただきました。
ナマでアイルランド音楽を聴いたのは久しぶりです・・・4、5年前に、アイルランド西岸のゴールウェイにあるパブで聴いて以来じゃないかと思います。この時は、当時の恋人すなわち今の奥方とふたりで、ダブリンやアイルランドの西岸を旅していました。そうです、ふたりとも密かにアイルランド好きなのです。
わたしがアイルランドに惹かれていったそもそもの発端は、初めてアイルランドに足を踏み入れた時にさかのぼります。学生時代の春休みにヨーロッパを旅している時、突然の思いつきで、ポルトガルのリスボンから空路ダブリンへ渡ったのです。それがすべてでした。
偶然にもその日は3月16日、つまりアイルランドで最も重要な祝日、セント・パトリックの日の前日だったのです。宿はどこも一杯で、20件ぐらい訪ね歩いて、12人部屋のベッドを一つ、やっと確保したのでした。
その日のパブには人があふれ、入りきれない人たちは外でギネスのグラスを傾け、その向かいの空き地ではミュージシャンたちが演奏をして人だかりができる・・・といった状態でした。そのなかに十数人の打楽器のグループがありました。服装も演奏スタイルもまったく飾ったところがなく、しかし不思議なエネルギーを秘めたその演奏に、わたしは衝撃を受けてしまいました。当時の日本はバブルの表層的繁栄の名残りをひきずっていた時代でしたが、虚飾と虚栄で飾り立てた派手やかな日常に疑問を抱いていたわたしは、アイルランドの飾りけのないこのパワーに、求めていた何かがここにあると感じたのでした。
アイルランドの持つパワーは、その辛く悲しい歴史によって培われたものだと思います。アイルランドは、巨大な隣国イギリスの植民地として、長きに渡る法的抑圧や差別を受けてきました。イギリスによる支配を800年以上にわたり受けてきた彼らは、イギリスにすっかり養分を吸い取られてしまった祖国を離れ、アメリカやオーストラリアに渡っていきました。特にアメリカには、19世紀中ごろから多くのアイルランド人が、死を覚悟で渡っていきました(映画『タイタニック』のタイタニック号にも、アメリカに向かうアイルランドの人たちが乗っていて、アイリッシュ・ダンスをしていましたね)。その結果、アイルランドは、北アイルランドを合わせても人口500万人くらいなのに、アイルランド系の人は世界に7000万人いるといわれています。・・・なんか授業のようになってしまってスミマセン?
今年のサッカー・ワールドカップでアイルランドチームがみせた脅威の粘りと底力にわたしは何度か興奮を覚えましたが、それが長きに渡る植民地支配の抑圧という苦しみを耐え抜いてきたゆえに出せる力だと思うと複雑な心境になります。
さて、肝心の今回のライヴ。セタンタのメンバーの名前や伺った経歴からすると、彼らもアイルランド系のようですね。今回の演奏では、アイルランドからアメリカへ渡った最初のカウボーイの歌があったりして、コテコテのアイリッシュというより、アイルランド音楽とアメリカのフォークソングの意外な近さを感じました。アメリカに渡った人たちが踊ったアイリッシュ・ダンスがタップダンスへと変化していったことを考えると、アイルランド音楽とアメリカのフォークソングにも何らかのつながりがあるのかもしれませんね。
うちの奥方は次のように申しております。 「今回の演奏は、土着のアイルランド音楽プラス、アメリカのクラブでの演奏で育まれた都会的なセンスを感じます。唄い方がロックやポップスとは違う、アイルランドに特有の、詩の朗唱に近いようなスタイルだったのが特徴だと思います。なかなか上手なバンドだったよね。」ちなみに彼女はアイルランドでアイリッシュ・ダンスの手ほどきを受けたことがあるハズ。
セタンタの三人はアメリカのシアトルを拠点に活動しているということで、公演前に伺ったところによると、シアトルは気候や自然の風景がアイルランドに似ているということでした。そのような理想的な風土が、このバンドの魅力の根底にあるのではないでしょうか。セタンタのメンバーを紹介します。フィンはギター担当。アイルランド音楽にギターってあったっけ?と一瞬思いましたが、このギターが、時にアメリカのフォークのフレーバーを少し加えながら、縦横無尽に活躍していました。個人的には、ギターという楽器の素晴らしさを再認識しました。
ハンズはアイルランド音楽には欠かせないティン・ホィッスルや、アンコールでは尺八まで披露してくれました。そして彼のヴォーカルにかぶさってくるデイルのフィドルの音色!心にしみいります。
アイルランド音楽といえば、リヴァー・ダンスで有名になったようなリールから、”Down by the Salley Gardens”のような静かな癒しの曲までありますが、今回のライヴではそのどちらもが楽しめました。ああ、これぞアイルランドのリズム、と思わせる、まさにパブで演奏されているような自然に身体が動いてくる曲もあれば、現代のアイルランドの曲、スコットランドに伝わる曲、そしてセタンタ自作の曲。静かな曲では会場はしんみりし、賑やかな曲になると一転、踊りだす人もちらほら。うちの子もノリノリでした。ロビーで販売したギネスが聴衆の気分をなごませ、また同時にテンションを上げました。
アイルランド音楽の独特のチューンって、久しぶりに聴くと、心の波長と一致するんですよね。セタンタの演奏を聴きながら、時にアイルランド西岸の自然の風景を思い出し、時にアイルランドのパブの活気と盛り上がりを思い出しました。
今回のライヴで唯一残念だったこと、それは・・・スタッフはギネスが飲めなかったことです!!
(岩井学・HVS)
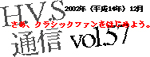 home●<>
home●<>