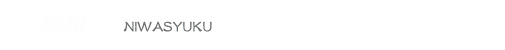![]()
庭宿 NIWASYUKU
代表 宿谷克也(シュクタニ カツヤ)
・1978年 滋賀県甲賀市水口町に生まれる。義務教育の9年間、無遅刻、無欠席で過ごす。中学、高校は部活動に燃え、日々汗を流す。大学は一転、講議にはあまり顔を出さず、一人暮しにうかれ友人と遊びまわる。試験は一夜漬け。なんとか卒業単位は、ほぼ3回生で取り終える。単位の心配がいらないので、就職活動は余裕をもっておこなえた。しかし、やりたい事がみつからず、さまざまな業種を受ける。結果、何社から内定をいただき、待遇の良かった会社を選ぶ。
・2000年4月 社会人になる。某建設会社に営業で入社。8月 某建設会社を約3ヶ月で退社。社会に出てようやく、仕事をする事の意味を考える。田舎育ちであり、幼少から自然にふれる事が多く興味もあった。イメージを膨らますとワクワクしてくる。方向性は、農業、林業、造園業に決まる。職安で某造園土木会社を見つけ、面接を受ける。結果、人生で始めて面接で落とされる。電話ごしに具体的な理由を聞くと「外仕事であり体力的にも大変な仕事なので無理では」ということだった。ならば、バイトでもいいから一度試して下さいと頼む。
・2000年11月 某造園土木会社に入社。一週間程して、社員として雇ってもらえる。造園業にかかわり、奥の深さはもちろん石や植物等の自然と向き合う仕事に惹かれていく。そして、庭が持つ空間の使い方に感動し魅了されていく。同時に趣味が減っていった。現場は造園作業から草刈りや土木工事、測量まで幅広くさせてもらい、会社勤めをしながら造園の職業訓練校にも行かせてもらう。しかし、土木工事の割合が年々増え、個人邸の剪定作業は少なく、庭の手入れに対する想いと焦りが強くなる。
・2004年4月 某造園土木会社退社。個人邸やお寺さんを中心に回っている某植木屋に無理を頼んで入らせてもらう。その時、親方の男気を感じる。現場では庭木剪定を中心に植物の管理方法や庭作り、石工事等を教わる。特に、日常の会話は興味深く、造園の話はもちろん世間話も非常に勉強になった。なにより親方は、一本筋が通っていて、人としての影響力は強いものであった。私自信、心にしみることが何度もあった。 独立については、前からボンヤリと想い描いていた事だった。新しい職場に就いて、1年が経った頃から独立の想いが強く湧いてきた。その後3・4ヶ月思い悩んでいたが、親方に相談してみる。親方は大賛成しなかったが、反対もしなかった。ただ、勢いのある時じゃないと、独立はなかなか踏み切れないと言ってもらえた。
・2005年10月 庭宿開業 ひとり親方で独立。
◎庭宿の日々
仕事をするからには、お客様には喜んでもらい、自分も気持ち良くありたい。そのためには、第一にお客様の満足を得られることが必要になってくる。これは基本であり、常に気をつけていることである。
まず、お客様探しでは、しつこいセールスはせずに必要としてもらえる所にお伺いしている。理想はお客様からの紹介で、輪が広がっていくのが理想である。
仕事を頂いたら、自分自身の全てを仕事にぶつける。その結果、仕事を認めてもらえば信頼関係が築けることになるし、認めてもらえなければ納得して手を退ける。このくり返ししかないと思っている。それと、忘れてはいけないのが安全第一。怪我や事故はお客様に迷惑をかけるし、自分も痛い。
普段、車に乗ってもきょろきょろしている植木屋さんは多いと思う。私もその一人である。土地柄、自然が間近にあるので、ついつい目がいってしまう。樹木をみると名前がまず口にでる。うんちくも並べたくなる。知らない樹木があると、黙る。単純だと自分でも思う。分からなかった樹木は家に帰ってからこっそり調べる。
他所の庭は特に目につく。これが、かなり勉強になる。手入れのやり方から庭の構成、全体の空気というか雰囲気など見るべきことは多い。基本的に植木屋は他の手を褒めることは少ない。ほとんどの植木屋は自分の手に自身をもっている。口に出す人もいれば、心の中で思っている人もいる。各々の感性が大きくでる仕事だからと思う。だからこそ、他の職人の感性が気になるのだと思う。
お客様の中には自分で剪定をされている方もいる。私は良い事だと思う。自分の首をしめているようなものだと笑われたことがあるが、やはり庭をさわることは楽しいものである。そして、そのような人が増えていくことは、やはり嬉しく思う。だからこそ、危険な高木だけの剪定や手の出しにくい松だけの剪定も受けている。病害虫防除や施肥などの仕事を、単発で受けることもしている。
仕事は真剣勝負である。当然、手は抜かないし、時間稼ぎもしない。というより、信用を落とす事がなにより恐いからできない。庭木剪定などでは、半端な時間に作業が完了することがある。そのときはお客様の確認がもらえたら作業を終える。当然、作業時間分だけ請求する。しかし問題もある。生き物相手なので毎年同じようにはいかないことがある。年によって請求額がかわると、正直、請求しにくい。大体の予算を相談してもらえると、目安になる。毎年同じ時間で仕上げるのも技術のひとつであるから、できるだけ予算に合うようにしている。しかし、予算的に考えて信用を落とすような仕上がりになるのなら、お断りすることにしている。
作庭を頼まれると、先ず会話からはじまる。お客様の好みや要望、なにより庭(デッドスペース)に何を期待するのか等を教えて頂く。予算的な事も含めおおまかなイメージがつかめると、設計に移る。設計ではとにかくアイデアをたくさん出す。なぐり書きで何枚も何枚もつくる。最終的に二つか三つに候補をしぼり、仕上げをおこなう。見積りも当然作るが、これがけっこう大変である。計画図面を考える時は時間を忘れ作業に没頭できるが、見積りを作る時はなかなか進まない。
見積りで目安になるのに物価本や積算マニュアル等があり、参考にはなる。しかし、一番頼りになるのは経験である。自分なりの施工単価で見積りを行うと、大抵が積算マニュアルよりも安くなる。おそらく、他の植木屋も同じだと思う。では業者によってでてくる価格の差は何なんだろうか?
先ず、経費。以前お世話になっていた造園土木会社ではよく社長が「一日で一人当たり五万円は稼がないと会社がなりたたない」と言っていた。確かに自分の給料分しか仕事ができなかったら、事務員さんや営業の方の給料は出ないし、仕事に使う車にも乗れなくなる。従業員を多数かかえている会社や機械を沢山持っている会社に比べると、経費がかからないのが規模の小さい植木屋の強みだと思う。ただ、規模が大きいとあつかうお金も大きく、値段競争をすると小規模の植木屋では歯がたたないこともある。
次に、材料費。当然、材料費は価格に直接ひびいてくる。仕入れ先によって価格の違いはあり、物が良く少しでも安い材料を探すことは非常に重要である。仕入れ先が固定されていると、楽ではある。しかし、新しい仕入れ先を探していくことは一番簡単な企業努力だと思う。で、業者によって材料費が違うことがあるのは何故だろうか。先ず、仕入れ価格の違い。それと、上乗せする金額の違いがある。この上乗せ金額の違いが、一番不透明なところである。少しでも儲けるために高い金額を上乗せする業者もいれば、技術にそうとうな自信があり、「同じ材料でも使い方が違うから」と高い金額に設定する業者もいる。逆に、安い料金で勝負する業者もいる。一般の方が適正金額を知るためには、相見積りをとるか、信用できる植木屋とおつき合いするしかないと思う。
技術料、施工費も材料費と同じで、業者のさじ加減で大きな差が生じるので、植木屋を信用するか相見積りをとるしかないと思う。
結局、庭作りのお値段はお客様自身が納得できるかできないか、だと思う。私の場合は、「出来るだけ安く、しかし、損はしない」を基本姿勢に見積りをつくっている。生活の糧として植木屋を選んだが、お金持ちになるために植木屋になったわけではないからだ。正直、高い価格で仕事をしている同業者をみると、羨ましく思うこともあるが、おそらく植木屋の根本が違うのだと思う。逆に、安い価格で仕事をする同業者にも同じことを思う。
そのような事もあり、計画図面と見積もりをお客様に見ていただく時は、緊張感や期待で内心落ちつかないものである。